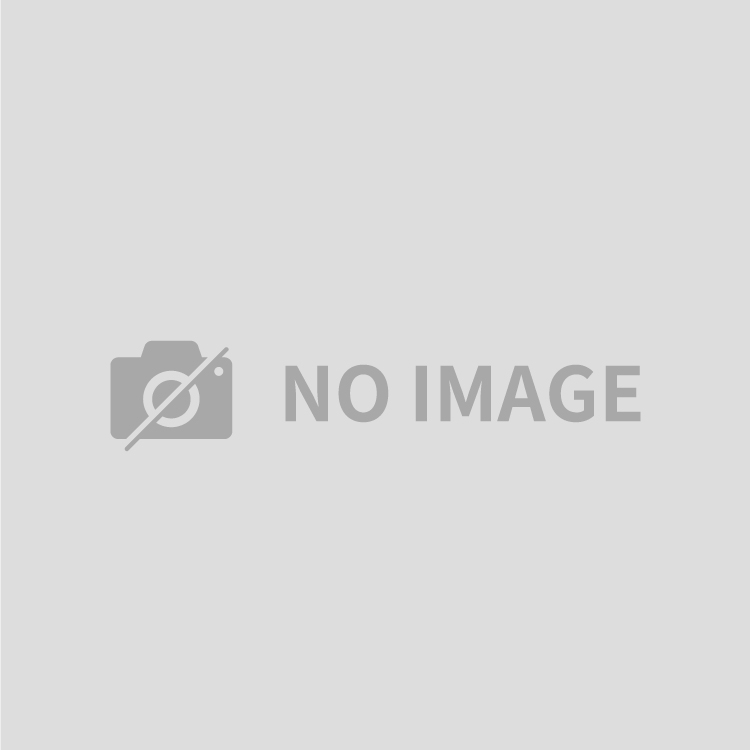50mm/hくらいの雨量でこのような状況になってしまう立石地区。毎年のことで以下のような要望書を藤岡市に充て提出いたしました。すぐに改善が見込めるものではないので、できることから対処していこうと思います。まずは自助に繋がる防災意識の向上から、そして共助の重要性の周知、今までもやってきましたが更に大きく、継続して行って参ります。




A.排水・構造面の整備強化
- 既存排水機能の早急な強化
側溝や排水路の浚渫・拡幅、グレーチングの整備、排水能力を超える箇所の流路再設計など、即応性の高い構造的改善の実施。 - 道路冠水対策の重点化
毎回同じ場所で冠水が繰り返されている市道について、現地調査を行い、盛土や舗装傾斜の見直しなど根本的対策の検討。 - 土砂災害リスク箇所の保全対策
斜面から土砂が流入した地点では、のり面保護や簡易な土留設置等を通じて予防的対策の早期実施。 - 区画整理事業の排水接続工事の早期完工と情報開示
現在、一部未接続の排水設備が内水氾濫の一因となっているとの認識に基づき、整備の進捗加速と地域への丁寧な説明の実施。 - 広域水系を見据えた排水計画の見直し
利根川、烏川、神流川、鏑川、鮎川といった周辺河川の水位上昇により排水が困難になる「内水氾濫」の傾向が見られます。外水との連動を考慮した排水計画の再設計。
B.災害時の運用と情報連携の整備
- 自主避難所としての運用体制確立
今後、内水氾濫や道路遮断により帰宅困難となる事態を見越し、地域づくりセンター小野等を迅速かつ柔軟に開設できるよう、体制づくりと基準の整備。 - 教育機関との情報共有と連携強化
今回、小野小学校が水道設備故障により休校となった際、地域見守り関係者には情報が届かず混乱が生じました。こうした連絡体制を強化し、学校・地域・行政間でのリアルタイムな情報共有を可能とする仕組みづくりの構築。 - 停電・雷雨時も機能する連絡網整備
従来の連絡方法に加え、携帯圏外や停電時にも最低限の情報伝達が可能となる連絡網や新たな情報伝達手段の導入などの検討。
C.生活支援体制と環境整備
- 災害ごみ・所有者不明物の処理方針の明確化と周知
内水氾濫によって発生した生活ごみや枯草、他宅から流れ出た私物等の処理について、 平時からの対応方針を明確化し、住民と共有することで災害時の混乱を軽減する体制整備の構築。 - ごみ集積場の災害対応マニュアルの整備と共有
地域の自主防災組織等と連携しながら、災害発生時における一時集積所の設置方法や、回収・仕分け体制などを整理した運用マニュアルの作成と普及の推進。